歯科コラム
かわいいだけじゃすまされない「お口ポカン」
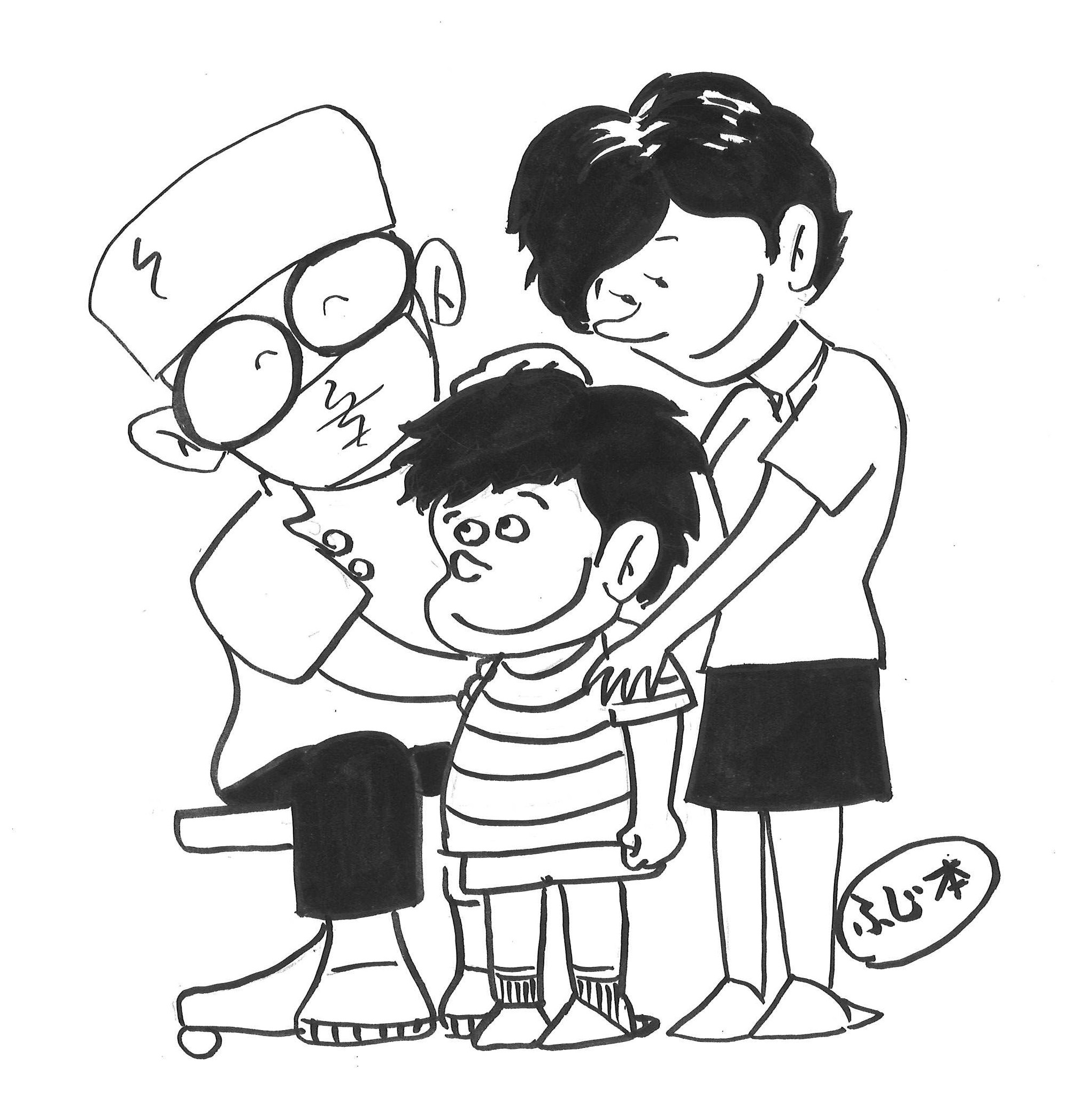
日本の子どもの約30%、つまり10人に3人が「お口ポカン」の状態にあることをご存知でしょうか。これは医学的には「口唇閉鎖不全症」と呼ばれ、安静時にも上下の唇が自然に閉じない状態を指します。
この「お口ポカン」は、単なる見た目の問題ではありません。口呼吸が主体となることで、本来鼻で行われる空気の加湿・加温・殺菌機能が失われ、ウイルスや細菌が直接口から侵入しやすくなります。また、口腔内の乾燥によりむし歯や歯周病のリスクが高まり、舌の位置が低くなることで歯並びにも影響を与えます。さらに、咀嚼や嚥下(飲み込み)機能の発達にも悪影響を及ぼす可能性があります。
2018年に医療保険制度で「口腔機能発達不全症」という病名が新たに認められ、現在は18歳未満の子どもが対象となっています。これにより、歯科医療は従来のむし歯治療中心から、「食べる」「話す」「呼吸する」といった口腔機能の発達支援へと転換しています。
口腔機能発達不全症の原因として、口周りの筋力不足、鼻詰まりによる口呼吸、舌の癖、現代の食生活による咀嚼不足などが挙げられます。コロナ禍のマスク生活も影響したとされています。特に指しゃぶりや舌突出癖などの口腔習癖が長期間続くと、開咬(奥歯は噛んでいても、前歯が噛み合わず隙間が空いた状態)や上顎前突(いわゆる出っ歯)といった歯列不正を引き起こすリスクが高まります。
家庭でできる対策として、正しい姿勢での食事、年齢に応じた硬さの食品提供、「あいうべ体操」などの口腔機能トレーニングが効果的です。歯みがき時に口元の観察を習慣化し、3~6カ月ごとの定期歯科健診で専門的なチェックを受けることも大切です。
口腔機能には発達の臨界期があり、早期発見・早期介入が重要です。気になる症状があれば、かかりつけの歯科医院で相談することをお勧めします。子どもの健やかな成長のため、この問題への理解と適切な対応が求められています。
